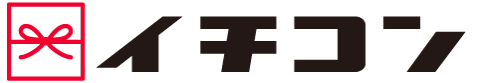AI小説「ザイム真理ヲ教ル」最終章

やり直す
「本当に久しぶりだ。再開したXを見て、懐かしくなって連絡したんだ」
黒のスーツを纏ったオメガは、口元に笑みを浮かべた。その姿は華やかなクラブの中で際立って異質だった。豪奢なソファやシャンデリア、きらびやかに行き交うホステスたち。浮かれた空気が充満する場にありながら、彼だけは鋭い眼光を放ち、場の熱気を冷やすような威圧感をまとっていた。
「俺もあの後、いろいろあった。財務省解体デモなんて馬鹿げていたよな。あの頃は陰謀論に支配されて、自分で考えることを放棄していた。恥ずかしい話だ」
グラスを軽く傾け、オメガは静かに笑った。
「けどな、自分の人生は自分で責任を持たないといけない。そう思うようになってから、全てが変わったんだ。俺は日本を出て、人生をやり直した。今はラオスで仕事をしている。マーケティングの会社を立ち上げて、だんだん大きくなってきてるんだ」
「ラオス……?」
ザイムは聞き慣れない国名を呟いた。
「そうか、お前は知らないか」
オメガは軽く笑い、説明を続けた。
「ラオスは東南アジアの国だ。タイとベトナムの間にあって、中国とも国境を接している。川沿いの町に拠点を置いて、日本向けにオフショアのマーケティングをやってる。まだまだ発展途上だが、だからこそ活気がある。日本なんかよりも、よほど未来を感じられる国だ」
「実はな、ザイム。お前を呼んだのは他でもない。ラオスで俺の仕事を手伝ってほしいんだ」
オメガは声を落とし、目を細めてザイムを見つめた。
「日本語ができるスタッフは貴重だし、俺にとっても昔から知っている人間の方が信用できる。……刑務所帰りなんて、日本じゃ誰も雇ってくれないだろう? だがラオスでは、そんな過去を気にする者はいない」
ザイムの胸がざわついた。彼の言葉は、痛いほど図星だった。タイミーで日雇いを続けても、明日が保証されるわけではない。ネットでは「違法性がある」との噂も目にした。もし本当にサービスが止まったら、自分はどうすればいいのか。
「お前も感じてるだろう? この国に居続けても、緩やかに死んでいくだけだと」
オメガの声は低く、だが強く響いた。
「自分で選んで、自分で歩け。……ただな、迷っている間にチャンスは逃げる。チャンスってのは“来るかどうか”じゃない、“乗るかどうか”なんだ」
グラスの中の氷が小さく音を立てた。ザイムは黙ったまま、目の前の男を見つめた。
(本当に……そうなのかもしれない)
日本に残っていても、就職口などある気がしない。支援団体に繋がっても、結局は「過去」を消すことはできない。だが、オメガが言うように――国を出れば、すべてリセットできるのではないか。
「日本にいたって、誰もお前を選ばない。だが俺は違う。俺はお前を選んだ。信じてるんだ」
オメガは静かに、しかし逃げ場を与えないような声音で言った。胸の奥で、何かが揺れた。
旅立ちの真理
ザイムは、乗ることにした。このままタイミーで働いていても緩やかに死に向かうだけだと思ったからだ。そこからは慌ただしかった。オメガはパスポートや飛行機の手配を細かくしてくれたが、日程がタイトだったのだ。ザイムはばたばたと身辺整理をしながら、自分がこれまで歩んできた証を消していった。自分が来た道は自分自身が選んだ道ではあったが、生まれ変わる自分には必要ないものだからだ。Xのアカウントも削除し、スマートフォンは支援団体に返却した。もはやここにいるのは全てを人のせいにして騒ぎ回るザイムではなく、自分で道を決め、責任を負う一人の男だからだ。ザイムは自分の本名を胸に刻んだ。もはやザイムはザイムではなくなったのだ。
出発の日、オメガはラオス人スタッフを二人連れて、ザイムの泊まっていたホテルに現れた。白いシャツを着た細身の若者で、無言でザイムに一礼し、手際よくスーツケースを受け取った。
「さ、行こうか」
オメガは穏やかな笑みを浮かべながら、ザイムの背を軽く押す。三人は並んでタクシーに乗り込んだ。オメガが助手席に乗り込み、ザイムはスタッフに抱えられるように後部座席の真ん中に、両脇にスタッフが乗り込んだ。オメガは何度も運転ルートを確認しながら時折、現地の天候や空港での手続きについて話し、ザイムの不安を和らげようとするような様子を見せた。
空港に着いた。フライトは定刻通りとなるようだった。ラオスからは現地スタッフが案内してくれるらしく、車で迎えに来てくれるという説明だったが、それを聞く時間もあまりなくすぐに出発の時間となった。
いよいよ搭乗ゲートの向こうに向かおうとするその時、オメガがザイムに言った。
「お前が来た道は、お前自身が選んだ道。そして、お前が行く道も、お前自身が選ぶ道だ。結果を受け入れ、自分に責任を持つのが人生だ」
ザイムは笑顔で頷いた。それこそが彼の求めていたものだからだ。だが彼はまだ知らない。行き先がゴールデントライアングルの強制労働施設で、オフショアのマーケティングとは特殊詐欺のかけ子だということを。最後までオメガはザイムに真理を教えなかった。ただ、ザイムが急に翻意して逃げ出さないかを監視するため、彼が搭乗するのをいつまでもいつまでも笑顔で見守っていた。
完