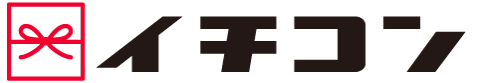AI小説「ザイム真理ヲ教ル」第6章

社会
ザイムが裁判を終えて社会に戻ったとき、彼は確信していた。
――自分は無罪だ、と。
逮捕も裁判も、すべて財務省が仕組んだ陰謀にすぎない。裁判など、無意味な茶番だった。世間は理解してくれるはずだ。俺は勝ったのだ。国家権力に打ち勝った唯一の人間なのだ。
しかし、現実は違った。
SNSでは自分の名前を打ち込むだけで、検索結果は「詐欺師」「妄想狂」「危険人物」といった文字で埋め尽くされた。ネットの事件記事は事実を列挙しているだけのように見えたが、ザイムには悪意の塊にしか思えなかった。「俺を貶めるための情報操作に決まっている」。そう何度も反芻するうちに、ザイムにとっての世界はすべて敵意に満ちていった。当然、就職活動も上手くいかなかった。
オレンジ
かつて熱狂した「財務省解体デモ」は、いまやすっかり下火だった。あの怒号も、あの熱狂も、今ではもう誰も口にしない。街の人々の関心は、すでに別のものへと移っていた。テレビや新聞は連日「好景気」「人手不足」を報じ、街頭には明るい求人広告や転職サイトの旗が踊っていた。街は陽気なオレンジに染まっていた。
それは、ザイムにとって残酷な光だった。
――人々は、もう財務省の陰謀を忘れたのか。俺が命をかけて暴こうとした真実は、何だったのか。
代わりに彼らが熱狂しているのは、オレンジ色の新しいムーブメントだった。笑い、歌い、未来を語り合う彼らの姿は、ザイムの胸を焼きつくす。
「人手不足なのに、なぜ俺だけが雇われない?」
面接に臨むたび、同じことを繰り返された。
「逮捕歴があるんですか?」
経緯を正直に語れば語るほど、面接官たちの目は冷え固まり、最後には決まり文句――「ご縁がなかった」――が突きつけられる。
夜ごと彼は布団の中でスマートフォンを握りしめ、自分の名前を検索した。コメント欄を何度もスクロールし、憎しみに満ちた言葉を一つひとつ暗記するように脳裏に刻んだ。その繰り返しの中で、ザイムはある「真理」に到達した。
――俺は正しい。間違っているのは社会のほうだ。
財務省はもちろん、マスコミも、企業も、人々の笑顔さえも。すべては腐敗し、虚飾にまみれた欺瞞の世界。だから自分が排除されるのは当然なのだ。社会が病んでいる証拠なのだ。オレンジ色に染まる街を見上げるたび、ザイムはその「真理」をますます強く確信していった。街を照らす光は、温かさの象徴ではなく「自分を照らさぬ光」。人々の未来を照らすオレンジは、自分を嘲笑する炎にしか見えなかった。
崩壊
ザイムの暮らしは、ついに崩壊の淵に立たされていた。面接に落ち続け、借金も出来なくなり、ある日、アパートの管理会社から退去通告の紙が投げ込まれた。冷たい活字が並んだ封書を見た瞬間、ザイムの頭は真っ白になった。行き場はない。誰も手を差し伸べない。社会全体が、自分を切り捨てようとしている。
その夜、ザイムはふらふらと街に出た。行き先などなかった。だが気がつけば、足は霞が関へと向かっていた。無意識のうちに、彼を追いつめた元凶の象徴――財務省へと吸い寄せられていたのだ。
深夜の官庁街はひっそりと静まり返っていた。ビルの谷間に街灯の光が落ち、舗道をオレンジ色に照らし出している。空気は冷たく、しかしザイムの胸の内は煮えたぎっていた。
財務省の玄関から若い女性官僚が現れた。何の苦労も知らぬように清潔で端正な顔をして、ブランド物の鞄や時計を身につけ、タクシーに乗り込もうとしていた。その瞬間、ザイムの胸に何かが突き刺さった。
熱いのか、冷たいのか、自分でもわからない。喉が締めつけられ、呼吸が浅くなる。視界の隅が暗く染まり、耳鳴りが膨れあがっていく。
――なぜだ。
――なぜ俺だけが。
――俺は間違っていない。間違っているのは……。
思考はちぎれちぎれで、言葉にならない。怒りと悲しみと妬みと苦しみが、ぐちゃぐちゃに絡み合い、彼の内側を掻きむしった。何を考えているのか、自分でももう理解できない。ただ胸が裂けそうに痛い。涙が出そうなのに、笑ってしまいそうでもある。嗚咽のような笑いが喉に引っかかり、呻き声に変わった。
タクシーのドアが開く音が聞こえた。
その瞬間、ザイムの全身が弾けた。
足が勝手に動く。拳が震え、血の気が頭に集まって視界が赤く染まる。
「お前たちのせいだ……! お前たちの、せいだッ!」
叫びと同時に、ザイムは突進していた。理由もない。説明もできない。ただ衝動だけが彼を突き動かしていた。
「畜生!お前たちのせいだ!俺をこんな目に遭わせやがって!」
ザイムは叫びながら、その若い女性官僚に拳を振り下ろした。女官僚の悲鳴は霞が関の闇夜を貫き、やがて警官が駆けつけ、ザイムは地面に取り押さえられたのだった。