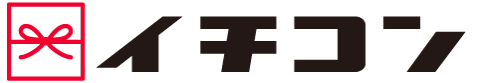AI小説『ザイム真理ヲ教ル』第5章

広告
知人がやってきた。この知人は広告代理店を経営しているらしく、オメガとは財務省解体デモの前から付き合いがあり、オメガからの策も預かってきたという。
知人の説明は次のようなものだった。財務省との戦いは熾烈なものになるだろうが、奴等には決定的な弱点がある。本来ならば通貨発行権を有する財務省とディープ・ステートは、通貨を無限に発行することでいくらでも工作員を雇ってSNSで工作活動をさせたり、電通や博報堂といった大手広告代理店を動かし世論を操作することが可能だが、それをすると通貨発行のウソがバレてしまい、彼らの拠り所とするものである国債発行は国民の負担であるという神話が崩れてしまう。そのため彼らも公表された予算制約の中で戦わねばならず、そこにのみ勝ち目があると。つまり世論戦に持ち込み、広告宣伝を大量に行うことで勝利することが出来る。
知人はそれを一手に引き受ける広告代理店として送り込まれたということだった。
「俺自身も今回が最終決戦だと思っている。正規料金じゃなくて赤字のバカ安で請けてやる。通常の3倍の広告を流す。負けたらなにもかもがおしまいだ。最後まで一緒に戦おう」
知人が提示した料金は、会社の総財産を上回るものだった。借金生活を終え、貯金を少しずつ貯め、家を買おうと思っていた資金も投入しなければならなかった。
ザイムは逡巡したが、最終決戦に挑むことにした。自分たちが財務省を倒せば、緊急放送によってこの赤字と同額が補填される上、その後は通貨発行権をこちらが握ることになり毎月給付金が出ると説明されたからだ。
被害者
ザイムが全財産を投入し、知人が運営する広告代理店に莫大な金を預けてから一ヶ月が経った。広告は大量に配信されたが、状況はむしろ悪化の一途を辿っていた。財務省への攻撃を強めれば強めるほど、逆にSNS上で批判や嘲笑が増え、組織内でも動揺が広がった。新規加入者は一人も増えず、残った”部下”たちも次々と抜けていった。
ザイムは焦りを募らせ、知人に何度も連絡を入れたが、「ここからが勝負どころだ。もう少しで財務省に勝てる」との返答が繰り返されるばかりだった。だが、勝利どころかザイムへの非難の声は高まるばかりで、状況が改善する兆しは一向になかった。
ある朝、ザイムが自宅で放心状態でSNSを眺めていると、玄関のチャイムがけたたましく鳴った。扉を開けると、そこには警察官が立っていた。
「警察です。話を聞きたいので同行してください」
ザイムは言葉を失い、何も言えないまま警察車両に乗せられた。取調室で初めて知ったのは、自分が詐欺容疑で告発されていたこと、今はまだ逮捕されていないということ、カツ丼は自腹であることだった。何かよく分からないが明らかに自分が危機に陥っていることを感じていたところ、正式に書類が来たということで正式に逮捕された。正式とそうでないものの違いはザイムには分からなかった。弁護士を無料でつけられると聞いたので、付けることにした。財務省解体デモでビラを配っていた女弁護士の顔が思い浮かび、一瞬迷ったが無料の方を選ぶことにした。ザイムにはもうお金がなかったからだ。
取り調べの中でザイムは己の知る真理を警察官に伝えた。
「財務省が仕組んだ罠だ!私こそが被害者だ!」
「財務省の犬め!さっさと釈放しろ!」
だが警察は冷静だった。警察は内閣総理大臣の所轄で国家公安委員会の管理下にあることを説明した上で、本当の被害者――ザイムが”部下”と呼んでいた者たちから告発があり、その証拠はすべてザイム自身が関与したことを指し示していると伝えた。
「その知人とやらは、あなた以外誰も見たことがありません。存在自体が疑わしい。現実を直視してください」
ザイムは全てが無駄だと悟った。財務省の犬でなければDSの手先だ。DSの手先には何を言っても無駄だ。ザイムは取調べの警察官に対し横柄な態度を取るようになった。当然、警察の追及は激しくなった。話は平行線が続き、拘留はどんどん延びた。
国選弁護士は時々やってきてザイムの話を聞いていたが、無駄だと思ったのか黙秘するよう伝えた。ザイムはそれを真実を語らせないようにするための陰謀と感じた。国選弁護士に報酬の出処を尋ねた。弁護士は法テラスという組織から出ている、法テラスは法務省所管の法人だと説明したが、今度はDSの手先かもしれないという疑念をザイムに抱かせた。やはりあの時の女弁護士に依頼するべきだと思い直したが、依頼費用はなかった。それもこれも財務省が緊縮財政を行いデフレ経済を引き起こしたせいに違いなかった。全てが仕組まれていたのだ。
裁判
裁判が始まった。ザイムにとって裁判所は異世界のような場所だった。高い天井、重々しい木製の壁、硬いベンチ。そこに座る人々は皆、黒い法服やスーツに身を包み、表情は硬く、言葉は難解だった。裁判官や検察官の話す言葉は長く、専門用語ばかりで、ザイムの耳には「〜罪」「証拠」「被告人」という断片だけが刺さった。内容は理解できず、ただ自分が責められていることだけは分かった。傍聴席にはインフルエンサーの裁判だということで数人、ライターらしき人物が座っていた。ザイムの知っている顔はなかった。
頼れるものは国選弁護士だけだったが、その弁護士はいつも同じことを繰り返した。
「黙っていてください。黙秘してください。私が話しますから」
しかしザイムは、自分が罠に嵌められたという信念を捨てなかった。何度も法廷で身を乗り出し、声を張り上げた。ライターに記事にしてほしかった。真理を伝えたかった。
「これは財務省の陰謀です!私は罠に嵌められたんです!」
そのたびに法廷は不気味なほど静まり返り、傍聴席からの冷たい視線がザイムに突き刺さった。弁護士は困ったようにザイムの肩を押さえ、裁判官に向かって深く頭を下げ、低い声で弁護を続けた。その姿が、ザイムには理解できなかった。なぜ謝る必要があるのか、自分は正しいことを言っているのに——
やがて判決の日が訪れた。ザイムは胸を張り、堂々と判決を待った。どうやっても財務省は真理を知った自分を処刑する必要があり、裁判もデタラメで死刑になると考えていた。せめて最後まで真理を訴えて死にたい、そう思って判決を待った。
裁判官の口から判決が告げられた。「懲役1年、執行猶予3年とする」
弁護士が小声で説明した。「執行猶予がつきましたから、刑務所に行く必要はありませんよ」
ザイムは混乱した。死刑ではない、刑務所にも行かない——そんなことがあるのか。心の中で何度も言葉を反芻し、やがて一つの理解を得た。「最終決戦に勝利したのだ。オメガの策がついに決まり、財務省を最後の最後で逆転したのだ、だから無罪判決になり、死刑にもならず刑務所にも行かないのだ!」
家に帰ったザイムは、SNSでその喜びを世界に宣言しようとした。しかしログインすると、アカウントは裁判中に凍結されていた。凍結解除まで数日かかり、その間に彼の高揚感は徐々に薄れていった。やっと復旧できた頃には、もう投稿する気力は残っていなかった。わずかに残った貯金も底をつき、生活のために働き口を探さなければならなかった。