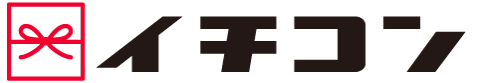稲盛哲学の終わりと「時間の経営」への変化

前回の記事をとあるサイトで公開したところ、大変反響が大きかったので続きを書いていきたいと思います。
商売の基本
まず、商売というのは「安く買って高く売る」というのが原則です。小売業や卸売業は高く売れるものを安く仕入れられるから存在しているビジネスで、製造業は高く売れるものを安く作れるから存在しているビジネスです。
なので、「高く売れるものを自分だけ安く仕入れられる・作れる」という状態を発見するのが金儲けの基本になります。私のようなコンサル業は知恵や知識を安く仕入れて高く売っている商売で、金融業は利子を預金として安く仕入れて貸出金として高く売る商売です。
国家レベルで言えば、「その国ではどういう資源が安く手に入り、何という資源が高く売れるのか」というのが重要になります。別に国でなくとも地域でも世界でも構いませんが「余っている資源を集めて、高価な資源に変換する」ということが国家繁栄への最短ルートになります。
これらの成功ルートを再現可能な形で表現したものが経営術です。ですので、経営術というのは国や地域、あるいは「その界隈」が安く買えるものや高く売れるものと外部環境との相互作用によって変わってきます。これが経営に絶対の正解がない理由です。
トヨタ生産方式と稲盛哲学
こうした中で、日本では長く「トヨタ生産方式」と「稲盛哲学」が優れた経営術であるとされてきました。昭和中~後期の30年はトヨタ生産方式が、平成の30年は稲盛哲学が優勢でした。優れた経営術は30年ほど有効なんですかね。私が考える「時間の経営」も30年ほどは有効であろうと思っています。
トヨタ生産方式というのは、工場においていかに生産性の高いものづくりをするか、という観点からムダ取り、ジャストインタイム、自働化、5Sといった取り組みを進めていくものです。
稲盛哲学とは、人としての正しい生き方を問い、動機が善であるか、私心がないかを問い、強い願望(ビジョン)を持ち、社内を小集団に分けて独立採算意識を持たせる活動(アメーバ経営)を行うというものです。
これらは日本型経営の一つの到達点とされており、昭和期において、また平成期において多くの経営者が見習うべき一つの形でした。
トヨタ生産方式や稲盛哲学が成立した社会状況
トヨタ生産方式や稲盛哲学が成立した背景には、当時の社会状況があります。
当時の社会状況を「ヒト・モノ・カネ・情報」という観点から整理すると、まず昭和期にはヒトとモノ(人材と資源)が大量に余っていた時代でした。石油ショックの直前だと原油は1バレル2ドルで取引されており、日本社会は人口ボーナス期で仕事の確保が政府には常に求められていました。一方で情報やカネは不足しており、かつ制限されていました。また戦後復興期でもあり、あらゆる物質的豊かさが不足していました。また、円安で世界が冷戦下の平和に覆われており、貿易がしやすかったというのも一つの大きな外部環境と言えるでしょう。
こうした社会状況のもとでは、物質的な豊かさを手に入れることが重要であり、安い資源や安い人材を使って物質的な豊かさを作り出すことが勝ち筋になります。よって、資源と人を効率的に使い生産性を高めるトヨタ生産方式が優れた経営術になります。加工貿易による輸出戦略も有効に働きます。
ところが、平成期に入ると外部環境が変化します。一つは情報化で、情報の価格が下がってきます。IT革命はそれを代表する出来事ですね。一方で新興国の成長(というよりも日本の模倣)が起き、製造業には強力なライバルが出てきます。人口ボーナス期は終わりましたが、就職氷河期のため人余りは相変わらずです。金融機関は体力がなく貸し渋りが起きます。
こうした社会状況のもとでは、人をどう使うか?ということが経営において重要なポイントになります。また、物質的には一応満たされた時代を迎えたため、心の豊かさが大事とされるようになりました。この状況下では「人はどう生きるか」という哲学を企業が与え、不況のもとで赤字を出さず、心の豊かさを売っていくのが正解になります。稲盛哲学の時代です。
この時期、同じような経営術がいくつか出てきています。代表的なのはワタミの経営術で、「地球上で一番たくさんのありがとうを集める企業」を理念とし、24時間365日経営のことを考え続け、夢に日付を入れ、お客様に心からのおもてなしをするという経営スタイルですね。ワタミはアメーバ経営の必要はありません。店舗ごとの採算管理をしていればそれがアメーバになるからです。
令和になって大きく変わった経営環境
令和の時代になると、この社会構造は再び変化します。少子高齢化による労働力の不足は隠す事が出来なくなり、不況もアベノミクスが終わらせました。人材の価値は急騰し、それが下がる見通しは当面ありません。化石燃料や鉱物などの資源価格は高止まりが続き、戦争も始まり国際的なサプライチェーン、つまりはモノの手に入りやすさが大きく下がりました。
一方で金融は金利高が始まったとはいえ緩和的な情勢が続き、資金調達は決して苦しくはなく、そして何より、情報化を超えて情報社会が到来した結果、情報はタダというのが当たり前の時代になりました。ちょうど昭和とは経営環境が真逆になってしまったということです。
こうした社会情勢の中では、時間が最も貴重な資源になります。人手が常に足りていないのですから、人の時間を取って働いてもらわなければならず、消費も短時間で効率の良い消費(タイパ)逆にラグジュアリーな時間を過ごしてもらうことが重要になります。私はこのラグジュアリーな時間の消費を「ラグタイ」と呼ぶことにしました。タイパの対義語です。
貴重な資源であるヒトやモノ、特に人の時間を創造したり(タイパ)、豊かにしたり(ラグタイ)することを目指す経営を「時間の経営」と私は呼んでいます。その際に安い資源である情報(デジタル技術)やお金(設備投資)などを上手く活用できれば、きっとものすごく儲かるでしょうね。
時間の豊かさを追求する時代
つまり私たちは、物質的な豊かさや心の豊かさを超えて、時間の豊かさを追求する時代に入ったということです。
具体例を挙げましょう。まずはタイパ経済から
吉野家は近年、メニューの多様化を進めています。これは吉野家が牛丼店から「タイパの良い店」に変化しようとしていることを示しています。早く美味しい物が食べられるお店への変化です。
オープンハウスもタイパ消費を志向しています。オープンハウスは非住宅的な楽しみをメインにする人向けのタイパの良い住宅、つまり駅近の狭小住宅を供給する企業で、近年急成長を遂げています。
サイゲームズの『ウマ娘 プリティーダービー』はここ数ヶ月でコンテンツの自動化を進めています。これはスキマ時間の奪い合いに勝利するためで、プレー時間の短時間化、オート化、一括処理といったアップデートが相次いでいます。
逆に、ラグタイ経済も静かに動いています。
体験型観光というコンテンツ開発が全国で進んでいます。地域の伝統やコンテンツを体験することにより、人生を豊かにしようというコンテンツで、伝統産業のグループワークから高僧の講話を聴くイベントまで、高付加価値な産業が興りつつあります。
労働環境改善ビジネスも盛んになっています。労働時間をラグタイ化し、採用に活かしたり定着率を上げようとする取り組みです。
とある有料SNSコミュニティも、ラグタイ経済として稼働しています。私たちはXやFacebookといった詐欺広告と虚栄心と無意味な言い争いが蔓延するが無料のSNSを既に持っていますが、そういうものから離れて、主催者を支持する知性ある人々だけが集まり、心理的安全性の高い環境で、長文を時間をかけて読み、落ち着いた議論をする、そういうラグタイな場所がそのSNSではないかと思われます。
想定する時間軸
この「時間の経営」は、今後30年ほどは経営術のメインであり続けると考えています。過去のトヨタ生産方式や稲盛哲学がそれぞれ30年続いたようにです。その理由は、30年ほど経過すると社会情勢(ヒト・モノ・カネ・情報の過不足)の関係が変化してくるためです。次に何が起きるかは予想は出来ません。戦争と恐慌によってモノとカネの流れが詰まり、失業者が続出する一方で情報も一層安く手に入る時代が来るかもしれない、核融合技術が発展し物質的制約が一切無くなるかもしれない、それは誰にも分からない未来です。
しかし私は、この時間を価値ととらえ、他者に時間を提供しようとする動き方こそが今後30年の間には支配的な経営術になる、と信じています。