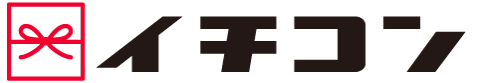ニデックと稲盛哲学の終わりの話
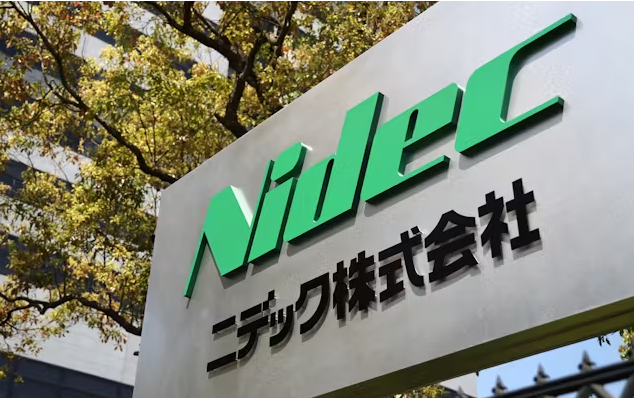
ニデックの有価証券報告書に対し、監査法人が「意見不表明」をしたという新聞記事がありました。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF260FR0W5A920C2000000
結局ここまで来ちゃったのかという気持ち
ニデック、旧日本電産ですね。永守イズムと呼ばれるほど信念の強い経営者である永守重信氏のもとで成長してきた企業ですが、ここ数年は曲がり角に来ていました。永守氏のお気に入りでない幹部はすぐにクビになったり、外部から人を呼んできても上手くいかなかったりと、とにかくゴタついていたイメージがあります。今回は、ニデックの転落とその原因、そして今後私たちがどうしていくべきかについて話します。
経営に対する思想の問題
今回のニデックの転落はひとえに、永守氏の経営に対する思想の問題であると考えています。一言で言うと、永守氏は時代の変化に経営思想を適合させることに失敗した。これに尽きます。
永守氏の思想は基本的には稲盛哲学です。稲盛和夫をとことん崇拝し「京セラのような会社になりたい」と公言してきた永守氏。近年は論語を経営に生かそうとする発言もありましたが、永守氏自身が独自の思想を持っているというよりも、稲盛哲学の忠実な実践者に近いですね。一方で急成長した企業で、かつ製造業(日本で最も生産性が高いのは製造業)であるにも関わらず社員の年収が企業規模の割に低く、人材の質も決して高くないことが窺えます。
思想の市場への不適合が原因
稲盛哲学というのは、理念経営(企業としての理念、生き方を最初に提示し、それを本に経営方針や手法を決めていく経営スタイル)のお手本のような経営スタイルで、平成時代に一世を風靡した経営手法です。稲盛哲学の「フィロソフィ」「考え方×熱意×努力」「アメーバ経営」といった考え方は、経営術を超えて人生の指針を示すようなもので、信奉する経営者は非常に多いです。
稲盛哲学の変調
一方で稲盛哲学(というより理念経営)は、令和になってからは徐々に社会不適合を起こしつつあります。知床遊覧船事故、ビッグモーター事件の背後には理念経営を謳うコンサルがいたことが知られていますし、稲盛哲学の一番の信奉者であった永守氏が率いるニデックは信用を失う寸前です。
アベノミクスが稲盛哲学を過去にした
稲盛哲学というのは、理念経営の中でも特に日本で発展した経営スタイルですが、これは稲盛和夫が日本人で、日本で成功した起業家であるということ以外にも、日本社会で受け入れられるべき素地があったためです。それは終身雇用制度と不景気です。
日本では戦後、終身雇用が素晴らしいという考え方が根付いてきました。これに伴い、転職市場は未発達でした。また、平成の長期不況は労働者から選択肢を奪い、今の会社で働くことを強いてきました。経営者だって決して楽ではありません。どうにかして明日を生き延びる術を考えなければなりません。
こうした経済環境と稲盛哲学は非常に適合的です。フィロソフィは自らの苦しい状況に意味を与え、アメーバ経営は赤字を作らない、生き残りの経営を志向しています。他に選択肢のない中で、今いる場所でいかに咲くかを考える経営スタイルは平成不況と共にあり、平成不況の中で「生きぬく術」として定着していきました。
稲盛哲学以外にも、平成不況に適合的だった経営スタイルがあります。「キャッシュフロー経営」です。ですがこれは本題とずれるのでまた別の機会に話す事にしましょう。
ところが、この稲盛哲学の繁栄を破壊した者がいます。安倍晋三です。アベノミクスによって雇用環境が好転し好景気と人手不足が始まりました。赤字を作らない経営ではなく、リスクをとって踏み出す経営が求められるようになり、労働者には転職先が与えられました。今いる場所で咲くことよりも咲ける場所を探すことの方が容易になりました。
理念経営は企業再生局面で赤字を作らないために求められるものとなり、それももはや消える寸前です。労働条件が悪化すると労働者が逃げ出すようになり、企業そのものも生存させるよりM&Aで売っぱらう方が手っ取り早く処理が出来るようになったためです。
稲盛哲学は「後ろに下がる」
かつて、稲盛哲学と同じように日本型経営のスタイルとして一世を風靡したものがあります。トヨタ生産方式です。トヨタ生産方式もまた、昭和中~後期に持て囃された経営スタイルで、それは単なる工場管理術に留まらず、人生の価値観として発展していきました。しかし日本社会で第三次産業が中心になっていくにつれ、トヨタ生産方式は後ろに下がっていきました。経営環境が変わり、最先端の経営スタイルとは見なされなくなったのです。しかし今でも、トヨタ生産方式は日本の経営者が学ぶべき教養です。
稲盛哲学もそのようになるでしょう。今後少子高齢化が進むことが決まっている中、人手不足は永久に解消しません。そうなれば人材は貴重な資源となり「今ここで踏みとどまり、置かれた場所で咲く」という生き方は少数派になるでしょう。来るべき、そして既に到来している新しい経営スタイル(これを私は「時間の経営」と呼んでいます)が主流となりますが、日本の経営者が学ぶべき教養となり、永遠に輝くことになるでしょう。
永守氏の失敗は
話を元に戻して永守氏の失敗は、この社会の変化、「時間の経営」に対応できず、稲盛哲学をベースに「社員には逃げ場がない」「コストを減らし、赤字を作らない経営」を前提として経営を行ったことにあると私は考えています。人がついてこなくなったか、幹部が追い込まれて不正会計に手を染めたか、いずれにしてもニデックの件は永守氏の失敗であるとともに、理念経営の時代が終わったことを意味しています。
なお、論語に関して言うと、論語を経営に取り入れた企業は予後が悪いことが多いですね。中国の古典は孫子の兵法を除くと全て皇帝による支配術なので、民主主義体制下の私企業に適用するには向いていません。
次の時代へ
次の時代は「時間の経営」になります。時間をどう節約するかや良い時間をいかに提供するかを基本としたもので、既に「時間の奪い合い」「余暇産業」「タイパ」などの言葉が出来てきています。既に気付いている経営者も多いので、これからの日本的経営はこちらに向かうことになるでしょう。